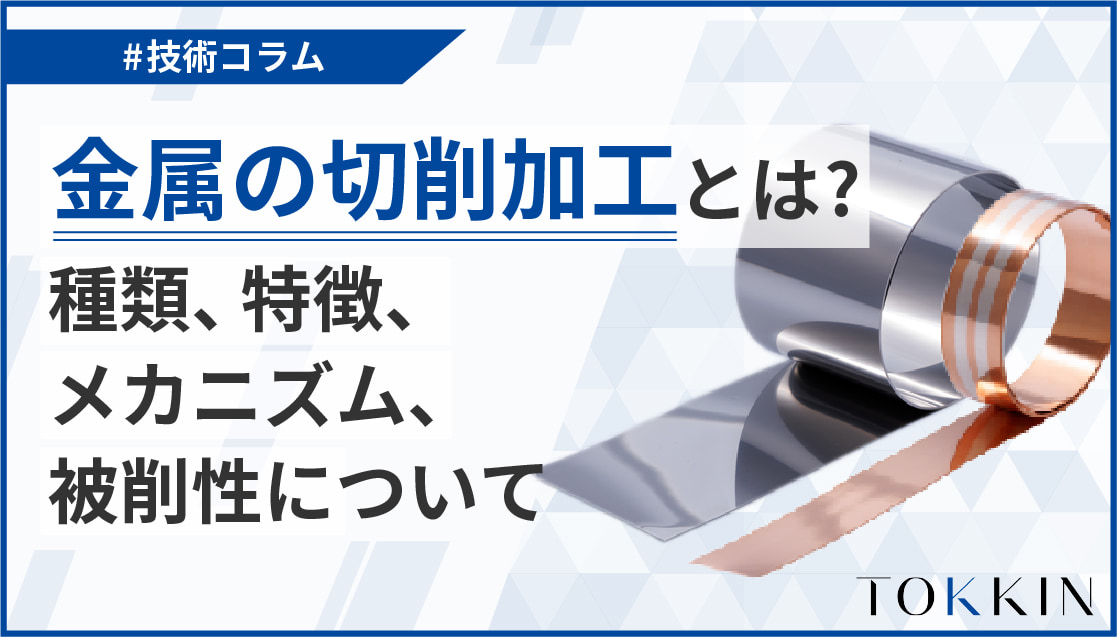
金属の切削加工とは?│種類、特徴、メカニズム、被削性について
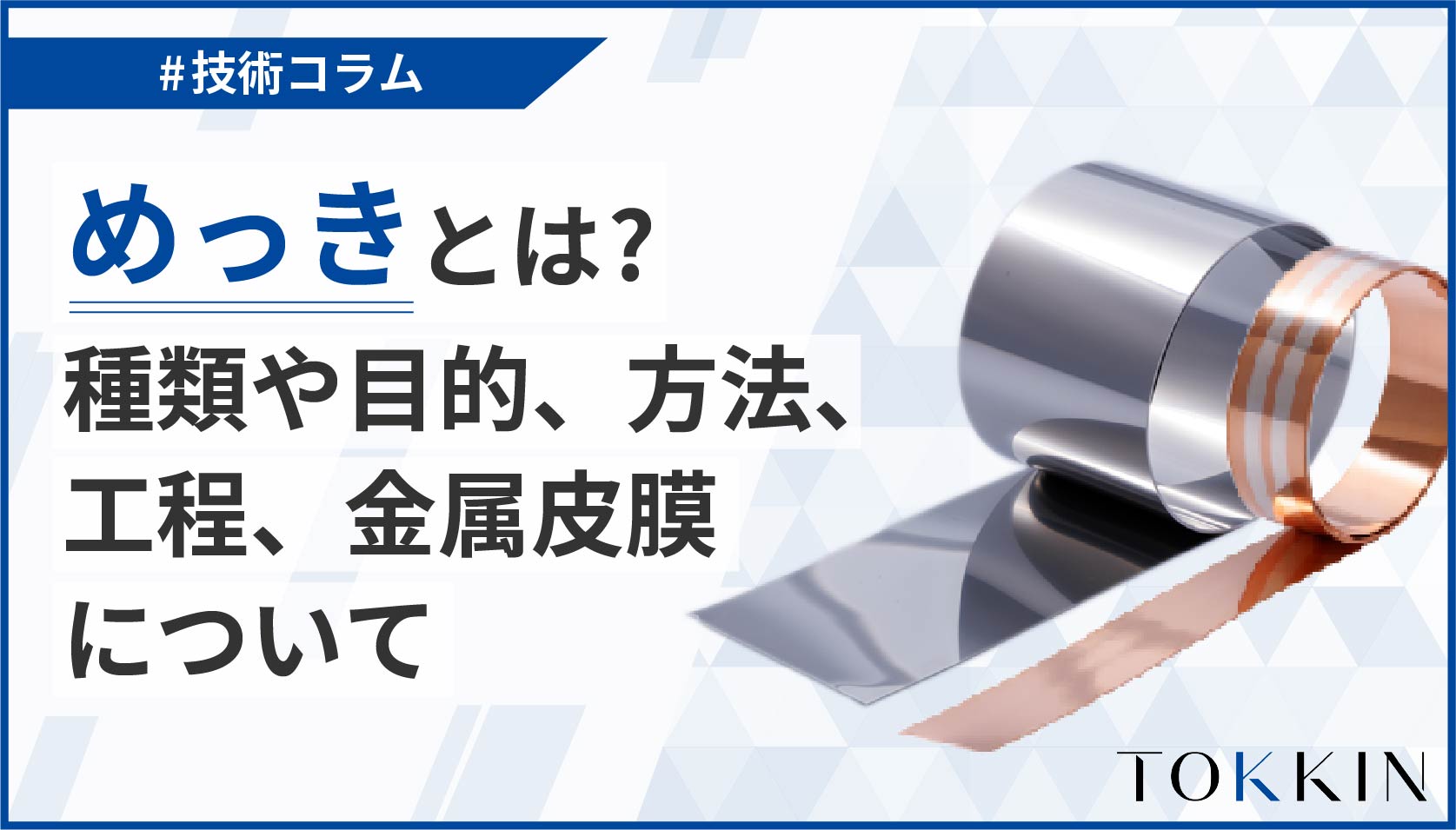
めっきとは、金属や非金属(プラスチックやガラスなど)の表面に銅やニッケル、クロム、金といった金属の薄い膜(㎛単位)皮膜をつける表面処理の一種です。当社は精密金属材料メーカーのため、ここでは金属素材に対するめっきを中心に説明いたします。
ちょこっとメモ
めっきの歴史はかなり古く、3500年前(紀元前1500年頃)にはメソポタミア北部にて、装飾品や鉄器などに錫めっきが施されていたとの記録があります。日本においては、古墳時代後期の700年頃に中国から仏教と共に伝わり馬具類や装飾品にその技術が使われてきました。
当時のめっきは、水銀に金を溶解した合金で青銅を覆い、それを加熱し水銀のみを蒸発させて金を付着させる方法であり、水銀中で金が溶け原型がなくなることから、「滅金(めっきん)」と呼ばれていました。
その後、次第に「鍍金(めっき)」と呼ばれるように変化し、現在は「鍍」が常用漢字ではない為、ひらがなや片仮名で書かれることがありますが、JISによる正式表記はひらがなで「めっき」となっています。
めっきには、いくつか種類があり下図のよう大別することができます。
湿式めっきとは、金属塩の水溶液から電気化学的に金属を析出させて 皮膜を形成する方法であり、電気めっきと化学めっきに分けることができます。
電気めっきは、電流を利用し金属皮膜を生成する方法で、電解めっきとも呼ばれます。
めっき中において、プラス極にめっきにする金属を、マイナス極にめっきをつけたい素材をセットし電流を流すとプラス極から溶けだした金属イオンが陰極へと移動し、陰極の製品表面で電子と結びついてめっき被膜を生成します。
コストが比較的安価で、錫めっき、金めっき、銀めっき、ニッケルめっき、銅めっきなどのめっき方法として利用され、連続加工が可能であるという特徴があります。
化学めっきは、電気を使わず化学反応によって金属皮膜を生成する方歩で、無電解めっきとも呼ばれます。
化学めっきは、置換めっきと還元めっきの2つに分けることができます。
めっき液中に還元剤を入れ、還元反応を利用してめっきを析出させる方法です。
還元めっきはさらに、非触媒型と自己触媒型に分けることができます。
非触媒型は、金属の水溶液に還元剤を入れ、還元剤の酸化反応により放出された電子がめっき液中の金属イオンと結びつくことにより、金属皮膜を析出させる方法です。
非触媒型は、めっき処理品の表面だけでなく液全体で反応が進む為、めっき浴の劣化が早く被膜の厚膜化は困難です。
自己触媒型は、非触媒型と同じく金属の水溶液にいれた還元剤の酸化反応により電子が放出され、めっき液中の金属イオンと結びつき金属皮膜を析出させますが、析出しためっき金属が還元剤の触媒として作用し、還元剤の酸化反応と金属の析出反応が連続的に続いていきます。
自己触媒型は、めっき時間にほぼ比例した厚膜を得ることが可能です。

イオン傾向の大きい金属をイオン化傾向の小さい金属イオンを含むめっき液中に入れると、イオン傾向の大きい金属が溶解し、金属イオンとなり電子を放出します。
ここで放出された電子が、めっき液中にあるイオン化傾向の小さい金属イオンと結びついて金属となりめっきを析出させる方法です。

乾式めっきとは、気体中もしくは、真空中など水溶液以外の方法でめっきをする方法であり、真空めっきと溶融めっきに分けることができます。
真空にした容器内で、金属をガスまたはイオン化して製品面に蒸着させる方法です。
真空めっきは、以下のPVDとCVDに大別することができます。
物理蒸着などとも呼ばれ、真空内でめっきにしたい金属を加熱し蒸発させプラズマなどによって表面に吹き付ける方法です。PVDはさらに、成膜方式によって真空蒸着、イオンプレーティング、触媒めっきに分けることができます。
化学気相蒸着とも呼ばれ、めっきにしたい金属の原子を含んだガスを使用し化学反応によりめっきを施す方法です。
溶融した金属のなかに製品を浸して被膜を付ける方法です。
被膜は厚く、均一性に欠けるが、加工コストが安いという特徴があり、デスクリート部品のリードや、トタンなどの大物の加工などに使われます。
様々な種類があるめっきですが、その目的は外観の向上、耐食性の向上、機能の向上の3つに大別することができます。
外観の向上の為に施されるめっきは、装飾めっきと呼ばれます。
アクセサリーやメダルなどの製品に光沢や高級感、金属感といった優れた美観を与えるために施され、代表的な装飾めっきとしては、装飾クロムめっきが挙げられます。
耐食性の向上の為に施されるめっきは、防食めっき(防錆めっき)と呼ばれます。
自動車部品や家電製品などといった製品を酸化、腐食から守るために施され、代表的な防食めっきとしては、亜鉛めっきが挙げられます。
機能の付与の為に施されるめっきは、機能めっきと呼ばれます。 電気伝導性やボンディング性、はんだ付け性、熱特性、磁気特性といった本来の製品の表面にはない機能を付与し、使用目的の働きを向上させるために施されます。
接点ピン、接点バネ、ケース、ダイオードやトランジスタなど個片部品をバレルに入れめっき槽中で回転させてめっきを付ける方法です。
一度に多くの製品にめっきを付けられるが、めっき厚のバラツキが大きく、細かいこすれキズが付くのが欠点となっています。

製品をひっかけといわれるラック治具にかけて治具を自動機でめっき層へ入れめっきを行う方法です。
大量生産はできないが、めっきの特性や外観にばらつきが少なく、プラスチックへのめっきやICの外装めっきに使用されます。
フープ上の製品をリールに巻き、先端よりラインへ導入しめっき付けリールに巻き取る方法で、フープめっきとも呼ばれます。大量生産に向き、品質のばらつきが少なく、プレス前の製品やプレス後の製品にもめっきができるという特徴がありますが、プレス後のめっきは製品形状により変形やめっき厚のばらつきが生じやすいという欠点があります。

ニッケル下地-錫めっきを例に、リールtoリール方式における工程を説明いたしますと下図のようになります。
アルカリ(NaOH)に界面活性剤を添加した液を使用し、液温は50~60℃となっています。
アルカリによる油脂の可溶化(ケン化)面活性剤による浸透・分散作用などによる脱脂を行います。
シアンアルカリに界面活性剤、キレート剤を添加した液を使用し、液温は40~60℃となっています。
製品をマイナス(一)極にして通電し、製品より発生する水素によって金属表面の酸化皮膜を還元除去します。
溶解した金属イオンはキレート材により封鎖され、素材への再析出を防止します。
錆、スケール、酸化被膜などを除去するために行われます。
10~20%硫酸または10~15%塩酸を用い、塩酸は加温するとガスを発生するので常温で使用します。
錫めっきは、ウィスカと呼ばれる被膜から発生する髭状の突起物が発生しやすいため対策として、ニッケルめっきや銅めっきで下地めっき施すことがあります。スルファミン酸ニッケル浴がニッケル下地めっきによく使用されます。
下地めっきの上に仕上めっきを施します。錫めっき浴は、酸性浴、中性浴、アルカリ性浴に大別され、用途や材料に応じて使い分けられています。
また、錫めっきは、はんだ付け性、耐食性、摺動性に優れているという特長があります。
製品に付着している水分を除去し、乾燥させます。
乾燥工程以外の途中工程は、めっきが大気に触れないように全て水の中に入れている状態で行われます。
熱伝導性、電気伝導性、密着性に優れており、また軟らかく展延性にも優れているため加工がしやすいです。
大気中の酸素や硫化物などと反応し変色しやすいため、使用環境には注意が必要です。
他の金属めっきの下地めっきやプ リント基板のスルーホールなどに使用されます。
美しい白さや金属中トップの熱伝導性、電気伝導性を持ち、また展延性が金に次いで大きく加工特性に優れています。
さらに、光の反射率が非常によく、抗菌性も備えているという特徴があります。
空気中で変色しやすく、特に硫化物の存在下では褐色~黒色に変色してしまいます。
電子部品やコネクタ端子などから洋食器、装飾品など幅広い分野で使用されています。
極めて高い耐食性と良好な熱伝導性、電気伝導性を持ち、柔らかく加工性に富むという特徴があります。
また、経時的変化による接触抵抗値の変化が小さく、はんだ付け性にも優れています。
他の金属に比べ非常に高価です。
ネックレスやイヤリングなどの装飾品から電子基板や半導体などに使用されています。
他の金属に比べて毒性が低いため人体への害がなく、はんだ付け性にも優れています。 また、摺動性、展延性、耐食性に優れているという特徴もあります。
ウィスカが発生しやすく、被膜が柔らかいため布でのふき取りで傷がつきやすいです。
また、融点が低いため高温で使用できないという短所もあります。
缶詰容器や食品用器具から接点部品、端子等の電子部品に多く使用されます。
耐食性、耐熱性に優れており、硬度が高いため耐摩耗性にも優れています。
また、変色しにくいため美観性の向上の為に多く使われるという特徴もあります。
光沢めっきは、被膜の硬度が硬いため二次加工時にクラックなどの不良が発生しやすいです。
また、無光沢めっきは、表面に指紋がつきやすく経時変化による変色が発生しやすくなっています。
他金属の下地めっきやアクセサリーなどの装飾品、電子機器などに使用されています。
TOKKINにおけるめっき加工については、こちらのページに詳細が載っていますのでぜひご確認ください。
また、当社ではめっき加工だけでなく、予備はんだとして利用されることが多い溶融はんだめっきや
最新記事
タグ